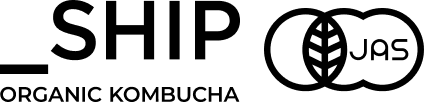お茶会に参加して「待つ」を感じた話

_SHIPのはじめです。
今回は、お茶会で感じたことを共有できたら。
あるお茶会で、お茶をたてる動作がどうしても遅く感じてしまうことがあった。
待つということ、いや待つこと以外にできないことで、
待つことに自覚的になり、今回の問いが立ち上がる。
待つという行為を通じて、待つ時間自体も心の持ちようで豊かにできるのでは。
普段の待てるということは心に余裕がある時、「お先にどうぞ」だけで、
相手の笑みを見られて、自分も幸せを感じることがある。
でもいつもそうできないのも事実。何かに追われるように、自分を優先している。
そんな時は掌を胸に置いて深呼吸と言いたいところだが、無意識に手が伸びたのは右後ろポケット。
少し暖かい。熱にも不感症になっている。輪をかけて驚く。
場のチカラを借りて強制的に待つことで行動が制限される。
身体が拘束されているのに、意識はおおいに全方向へ散らかっていく。
まだお茶はこない。何か動作をしてもいいきっかけが欲しい。
何を得るために、ここにいるかと自分に問う。おいしいお茶を飲むこと。
情緒的なことを省いて、合理的な作法を求めている。
嘘だ。
嘘だ。
無駄を愛した感性はどこに。
同じ思考が頭をループしては消える。
様々に彩色された景色が高速でストロボになって網膜に映る。
シャットダウン。
頭が真っ白とはこのこと。
今できることができない。
つい手が伸びてしまうスマホへの意識に抗うことも現代的な待つと捉えてみる。
ストレスには過去と未来にしかないという教えを友人から聞いたのを思い出す。
待つとは今に向き合う作業。
固定化されていた感性が時間と共にほどけていく。
時間と自分が一体化していく。
お茶会の話にもどる
美味しいお茶にたどり着くために
自分自身の観察に目を向けていると1杯のお茶が目の前に
まずは玉露
ほんの数滴、5滴くらいだったと思う
ここまで待たせて5滴!?と思ったが飲んでみたら旨味が凝縮されていて脳がハッとした。
そのあとに出てきた野人が作るお茶が今も忘れられない。
お茶から感じる海の旨味は煮干しのよう枯れた味が交差して…
なんというか1口目の衝撃はすごかった。時間の経過でも変化していく味わいに虜になり、
何度も杯を継ぎ足してもらった。
この茶葉を買いたかったが、さすが野人の作るお茶
作る時期が決まっていないらしく販売用の茶葉がないとか。
空腹を満たせるわけでもなく、のどの渇きを潤す為でもない。
沈黙の中遂行されたお茶会では、自問自答を超えて、小さな茶室から別の時空を飛ぶ。
あっという間のお茶会。
飲むという行為が生理的欲求と切り離されて、お茶を楽しむことに初めて触れた。
そう考えると、お茶会もどこからがスタートなのかはっきりしないとも言える。
待つということは今と向き合い、次の動きの反動をしっかりと受け取る以上に感じた
自分の変化。
他からみれば姿勢もかえず全く変化しない自分だろうけど、
私が自分を観察することですでに変化がうまれている。
いつもの行動に少し「待つ」を取り入れて、
足早な意識をそぎ落として時間を過ごしてみる大切さを感じた。